
社員の給与を公正かつ魅力的に|給与決め方のポイントと注意点
- カテゴリ: 人事・労務
- 公開日: 2024/6/24
この記事では給与体系の基本構成から、その意義や役割、さらには業務内容や市場の相場に応じた給与の設計方法について詳しく解説します。
給与体系を適切に設定することで、従業員のモチベーション向上、業績改善、そして組織全体の目標達成に大きく影響します。
給与体系の見直しを検討している方やこれから社員を雇用しようと考えている経営者に、必見の内容です。
目次
1. 給与体系の基本構成とは?

給与体系とは企業が従業員に支払う報酬の構造や方針を定めたもので、その会社の戦略や文化、業界標準に基づいて設計されます。
給与体系は基本給、職務給、能力給、賞与など、複数の要素で構成されることが一般的です。
1-1. 特に重要なのが基本給
基本給とは残業代や各種手当を除いた、給与の根本となる賃金です。
月々の給与計算は、この基本給に各種手当を加算し、さらに税金や社会保険料を控除して支払われる金額となります。
ただし、基本給が高いというだけで月収が必ずしも多いわけではなく、実際に手元に渡る金額は基本給とは異なるため、その違いを理解しておくことが重要です。
基本給には、残業代や変動手当、ボーナスなどが含まれません。
これらは基本給の外で計算され、給与の総額に加えられる要素です。
1-2. 業務内容によって給与を変えられる職務給
職務給とは従業員の担当する業務内容に基づき給与が決定される制度です。
このシステムでは年次や役職は給与決定の主要な要因とはならず、成果主義に似た特徴を持っています。
例えば、従来の「人材を仕事に合わせる」のではなく、「仕事に合った人材を採用する」というジョブ型雇用と密接に関連しています。
2. 給与体系を設計するときのポイントと注意点

給与体系を適切に設計することは、従業員の行動やモチベーションに大きな影響を与えるため、組織運営において極めて重要です。
ここからは給与体形を設計するときのポイントと注意点をご紹介します。
2-1. 給与のバランスを考える
給与の構成要素として、基本給、職務給、能力給のバランスが重要です。
通常、基本給は年齢や勤続年数による報酬が中心で、職務給は役職に基づいて支給されることが多いです。
一方、能力給は特定の専門技能を持つ職員に対して追加で支給されることが一般的です。
例えば、経験を重視するビジネスモデルでは、基本給の割合を高く設定すると良いでしょう。
また、組織の連携を強化したい場合は、職務給を引き上げるのが効果的です。
専門スキルが必要とされる研究分野などでは、高い能力給を設定してスキルの高い人材を適切に評価し、動機付けると良いでしょう。
2-2. 賞与(ボーナス)の種類
賞与は企業が従業員に支払う追加的な報酬で、主に「夏季賞与」と「冬季賞与」の二つに分類されます。
また、業績連動型ボーナスなどの特別賞与もあります。
計算方法は企業によって異なりますが、一般的には「基本給の数か月分」として計算されることが多いです。
例えば、従業員の基本給が30万円で、夏季賞与が基本給の2か月分とされている場合、60万円が夏季賞与として支払わます。
また、業績連動型ボーナスの場合は企業の業績や個人の評価に応じて変動します。
例えば、年間の目標達成率が100%を超えた場合に基本給の10%をボーナスとして支給するといった方式です。
2-3. インセンティブの設計
インセンティブとは、従業員のモチベーション向上を目的とした報酬制度です。
インセンティブ制度は賞与と違い、現金だけでなくプリペイドカードやギフトカードのような非現金報酬です。
インセンティブ制度は歩合給とも異なり、成果に応じた固定割合ではなく、多種多様な形で評価が行われます。
金銭的な報酬以外にも、成果に応じて表彰や昇進を行うこともあります。
2-4. 諸手当の種類
諸手当は基本給に加えて提供される給与の一部で通勤手当や住宅手当、家族手当、時間外労働手当などが含まれます。
通勤手当は、従業員が職場までの交通費を自己負担しないように設計されています。
例えば、公共交通機関を使用した場合の月間利用料が2万円だとすると、その全額を企業が通勤手当として支払うことが一般的です。
この手当により、従業員は通勤の経済的な負担を感じることなく、毎日の出勤が少し楽になります。
また、住宅手当は従業員が住宅を借りる際の費用を支援するための手当です。
住宅の賃貸料に対して、例えば月5万円までを企業が補助することで、従業員がより快適に働けます。
家族手当は従業員の扶養家族を支援するために設けられている手当です。
扶養している配偶者には月5千円、子供一人につき3千円が支給されることが多く、これにより家族全体の生活の質が向上します。
時間外労働手当は法定労働時間を超える労働に対して支給され、基本給の25%以上の割増が一般的です。
2-5. 社会保障の負担額を忘れない
社会保険料の負担額は給与の増加に伴い高くなります。
2024年度の日本において、社会保険料は従業員と会社が共同で負担する形式を取っています。
具体的には、厚生年金保険料は18.3%、健康保険は地域により異なりますが、大体10%前後、介護保険料は1.60%です。
社会保険料の増加は、給与が増えることによって保険料の基礎額が上がるため、特に昇給や昇格の際には注意が必要です。
従業員の実質的な手取りが増えることは、モチベーションの維持に直接的に関わりますので、社会保険料の影響を適切に管理することが企業にとって重要です。
3. 相場に合わせた給与を設定する

多くの企業が業界の給与水準を基準にして給料を決めていますが、近年では異業種間でも人材獲得のための競争が激化しています。
特にIT業界など、競争が激しい分野では適切な給与設定が求められます。
ここでは、職位別の給与モデルを見てみましょう。
例えば、新卒採用では初任給は25万円前後に設定されています。
これは、多くの中小IT企業が採用時に設定している標準的な金額です。
次に、プロジェクトマネージャーの役職では、35万円前後の給与が一般的な課長職と同等です。
業界や地域の相場に合わせた給与にすることで、払い過ぎを抑えながら、社員を長く雇用できるようになります。
4. 忘れずに確認すべきこと
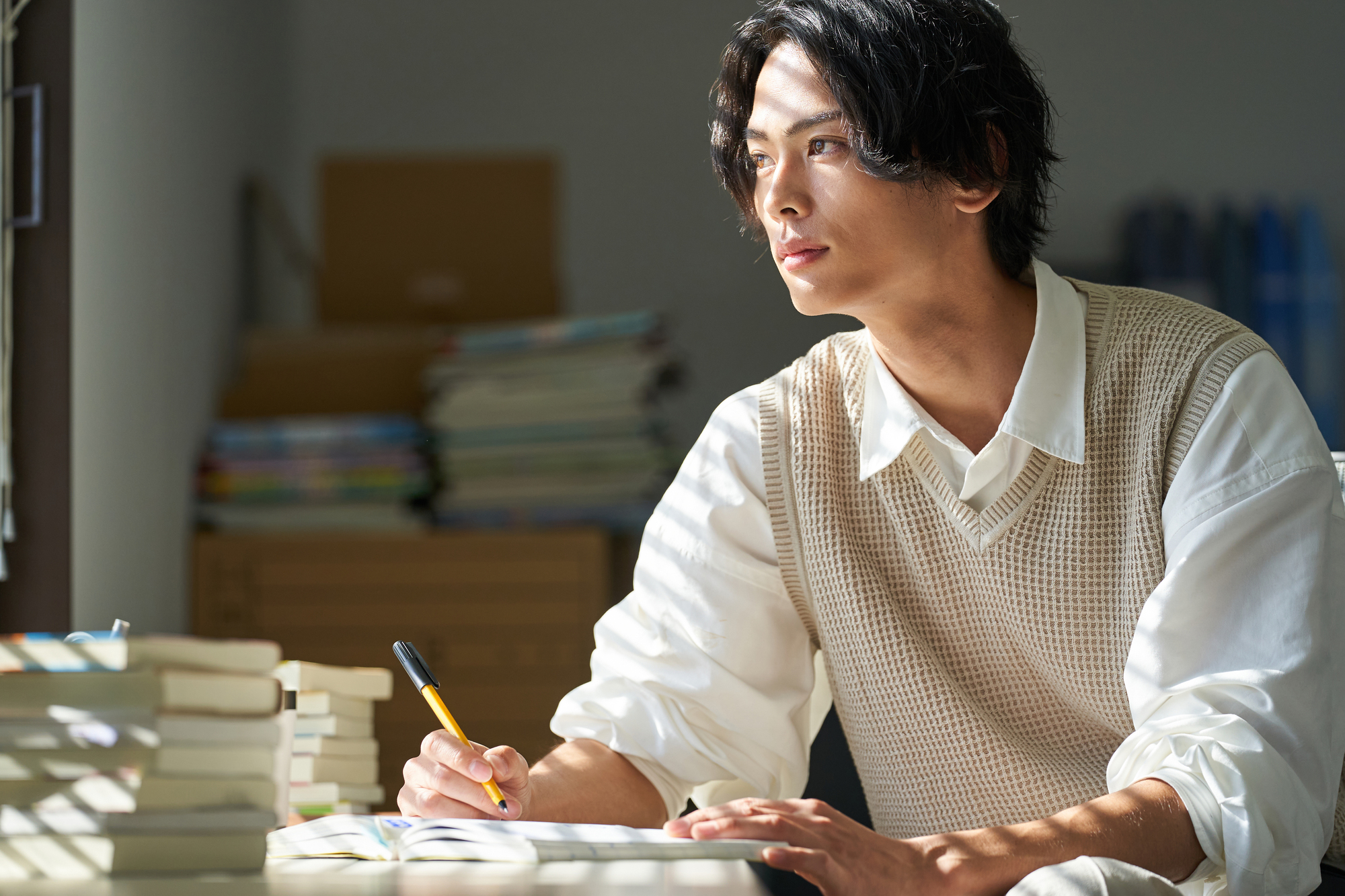
従業員を雇用する際、給与額の決定だけでなく、社会保険の加入手続きや法定三帳簿の準備が必要となります。
特に初めて従業員を迎え入れる場合には、以下の点に注意して準備を進めましょう。
4-1. 五原則の遵守
労働基準法第24条に定められている「賃金の五原則」を守り、給与は「通貨で」「労働者に直接」「全額を」「毎月1回以上」「一定の期日に」支払う必要があります。
これらの原則を遵守することで、法的にも問題なく従業員を雇用できます。
4-2. 法定三帳簿の作成
「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を含む法定三帳簿の作成は、従業員を雇用する際には避けて通れない重要な手続きです。
これらは事業場ごとに個人別に作成し、原則として5年間の保存が義務付けられています。
適切な帳簿の管理は将来的なトラブルを避けるために不可欠です。
5. 効果的な給与体系の構築が企業成功の鍵

給与体系は企業と従業員にとって非常に重要な要素です。
基本給、職務給、能力給、賞与などこれらのバランスをとることが大切。
特に業務内容に応じた職務給や特定のスキルに基づく能力給は、成果を正しく評価するために不可欠です。
また、市場の相場に合わせた給与設定により、競争力を保つことができます。
他にも五原則を守ったり、帳簿を忘れたりしないように気を付け、長く続けたくなるような会社作りを始めましょう。